「2級ボイラー技士試験」自体は、日本ボイラ協会のテキストから出題がされます。
(2級ボイラー技士教本)
おすすめの勉強方法は、理解度を優先するなら、同じく日本ボイラ協会から発行されている「最短合格 2級ボイラー技士試験」を全ページやることで、必要なら周回します。
この書籍の問題を解いていき、解説の大半が理解できるようになっていれば、どんな問題が出題されても十分に合格が可能だと思います。
(がっつり勉強する時間が確保できれば、1ヵ月程度でも合格可能だと思います)
様々な参考書を読みましたが、この書籍が一番イラストが多くてイメージしやすく、解説もわかりやすかったので一番おすすめです。これ一冊あれば良いと思います。
時間が無い場合は、評判の良いこちらの過去問でも合格が可能だと思います。
ボイラーの点火前、点火、停止後
ボイラーの点火前の点検・準備
・水面計によってボイラー水位が低いことを確認したときは、給水を行って常用水位に調整する
・験水コックがある場合には、水部にあるコックから水が出ることを確認する
‣つまり、水部にある験水コックから水が出ないということは、水位が安全低水面以下になっているということなので、常用水位になるまで給水を行います
・圧力計の指針の位置を点検し、残針がある場合は予備の圧力計と取り替える
‣残針があるということは、正確な圧力を示していないことになる
・水位を上下させて水位検出器の機能を試験し、設定された水位の上限及び下限において正確に給水ポンプの起動、停止などが行われることを確認します
・煙道の各ダンパを全開にしてファンを運転し、炉及び煙道内の換気を行って、炉内の未燃ガスおよび燃焼ガスを空気と置換する。これをプレパージという
油だきボイラーの手動操作による点火
・通風装置により、炉内及び煙道を十分な空気量でプレパージして、残留している未燃ガスや燃焼ガスを排除する
・点火前に、回転式バーナではバーナモータを起動し、蒸気噴霧式バーナでは噴霧用蒸気を噴射させる
・バーナが上下に2基配置されている場合は、下方のバーナから点火します
・燃料の種類及び燃焼室熱負荷の大小に応じて、燃料弁を開いてから2〜5秒間の点火制限時間内に着火させる
・着火後、燃焼状態が不安定なときは、直ちに燃料弁を閉じてから、ダンパを全開にします
ガスだきボイラーの手動操作による点火
・ガス圧力が加わっている継手、コック及び弁は、ガス漏れ検出器の使用又は検出液の塗布によりガス漏れの有無を点検する
・通風装置により、炉内及び煙道を十分な空気量でプレパージする
‣煙道内に未燃ガスが残留している可能性があるため
・点火用火種は、火力の大きなものを使用する
‣失火を防ぐため
・燃料弁を開いてから点火制限時間内に着火しないときは、直ちに燃料弁を閉じ、炉内を換気する
・着火後、燃焼が不安定なときは、燃料の供給を止めます。換気を行い、もう一度着火作業を行います
油だきボイラーの燃焼の維持及び調節
・加圧燃焼では、熱損失の防止や安全の観点から、断熱材やケーシングの損傷、燃焼ガスの漏出などを防止
・蒸気圧力を一定に保つように、負荷の変動に応じて空気量及び燃料供給量を調節して、燃焼量を増減する
・燃焼量を増すときは、空気量を先に増してから燃料供給量を増す
‣燃料供給量から増加させると、不完全燃焼によりばいじんが発生し、二次燃焼の恐れがある
・空気量が適量である場合には、炎がオレンジ色で、炉内の見通しがきく
・空気量が多い場合には、炎は短い輝白色で、炉内が明るい
・空気量が少ない場合は、炎が暗赤色で煙が発生し、炉内の見通しがきかなくなる
・空気量が適量である場合には、炎がオレンジ色で、炉内の見通しがきくようになります
突然、異常事態が発生して、ボイラを緊急停止するとき
(通常の停止操作とは少し異なる)
ボイラを緊急停止しなければならない場合に優先的にすべきことは、燃料を停止してから、炉内及び煙道を換気して、炉内を冷却することである
1.燃料の供給を停止します
2.炉内及び煙道の換気を行います
3.主蒸気弁を閉じます
4.必要な場合は、給水を行い、必要な水位を維持する
5.ダンパは開放したままにしておく
この順番は常に共通しているので覚えておく
①燃料供給停止
②換気
ボイラーの運転を終了するとき
(一般的な操作順序)
燃焼を止めた後、換気を行いつつ、ボイラー水位の低下を防ぐことが大切である
1.燃料の供給を停止します
2.空気を送入し、炉内及び煙道の換気を行います
3.給水を行い、圧力を下げた後、給水弁を閉じ、給水ポンプを止めます
4.蒸気弁を閉じ、ドレン弁を開きます
5.ダンパを閉じます
油だきボイラーの点火時、逆火が発生する原因
逆火(バックファイア)とは、燃料ガスの噴出速度よりも燃焼速度が速くなり、バーナ配管に火炎が逆走する現象をいいます
・煙道ダンパの開度が開いてない場合、煙道誘引が無いので炉内がプラス圧になりやすくなり逆火の危険があります
・点火タイミングが遅れた場合、油が炉内周辺に飛び散っている事が考えられ、
火が付いた時に一気に燃え広がり逆火する可能性がある
・点火用バーナの燃料の圧力が低下している時は、燃料の噴出が弱いので逆火の危険があります
・複数のバーナがある時は、一方のバーナでもう一方のバーナに点火してはいけない
煙道内に、すすの堆積が多いとき、又は未燃ガスが多く滞留している場合は、点火をしてはいけない。とても危険で爆発の可能性があるので、煙道清掃及び炉内パージを行うべきである。
ボイラーの停止後の措置
・運転停止のときは、ボイラーの水位を常用水位に保つように給水を続け、蒸気の送り出し量を徐々に減少させる
・ボイラーの燃焼側及び煙道はすすや灰を完全に除去して、防錆油、防錆剤などを塗布する
‣ボイラー休止中の保存状態が悪いと、腐食を生じる場合がある
・運転停止のときは、燃料の供給を停止してポストパージが完了し、ファンを停止した後、自然通風の場合はダンパを半開とし、たき口及び空気口を開いて炉内を冷却する
‣ポストパージとは、ボイラーの運転終了後に行う換気のことで、炉内及び煙道内の未燃焼ガスを排除する
‣全開にすると煙道ダクトが急激に冷却され,温度変化による不同膨張が発生し破損する恐れがある
・給水弁及び蒸気弁を閉じた後は、ボイラー内部が負圧(大気圧より低い圧力)にならないように空気抜弁を開いて空気を送り込む
・ボイラー水の排出は、ボイラー水がフラッシュしないように、ボイラー水の温度が 90°C以下になってから、吹出し弁を開き、ボイラー水を排出する
‣フラッシュとは、圧力変化により飽和水から蒸気に状態変化する事
ボイラーの水管理
・水溶液が、酸性かアルカリ性かは、水中の水素イオン(H⁺)と水酸化物イオン(OH⁻)の量で定まる
‣水素イオンが多いと酸性、水酸化物イオンが多いとアルカリ性となり、同量なら中性となる
・指標としてpH(水素イオン指数)があり、常温( 25℃ )でpHが7未満のものは酸性、7が中性、7を超えるものはアルカリ性である
‣pHは、-log[H+]と定義されています
酸消費量
・酸消費量とは、ボイラー水のアルカリ性分を示す数値のことである
・ボイラーでは腐食を防ぐために、ボイラー水をアルカリ性としている
・酸消費量とは、ボイラー水中に含まれる水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩などのアルカリ性分の量を示すもので、炭酸カルシウムに換算して、試料1L中のmg数で表したものである
・酸消費量とは、アルカリ分を中和するのに必要な酸の消費量を計測します。
‣酸消費量の「酸」とは、水のアルカリ分を中和するために用いられる
・酸消費量には、酸消費量( pH4.8 )と酸消費量( pH8.3 )がある
‣それぞれ、pH指示薬であるメチルオレンジ及びフェノールフタレインの変色点です
‣指標には2つの場合がある。ひとつは pH4.8までに中和するのに必要な酸の量を計測する場合と、もうひとつは pH8.3までに中和するのに必要な酸の量を計測する場合である

水の硬度とは、水中に含まれるミネラル類のうち、カルシウムとマグネシウムの合計含有量の指標をいう
このミネラルのうち、水に溶けるとカルシウムイオン及びマグネシウムイオンになる物質を硬度成分といい、硬度成分が溶けている水を硬水という
ボイラー水中に硬度成分があると、ボイラー内で蒸発により凝縮され、スケールとなって付着し、伝熱部の過熱を引き起こしてしまうので、制限されている
・カルシウム硬度
水中のカルシウムイオンの量を、これに対応する炭酸カルシウムの量に換算して試料1L中のmg数であらわす
‣「〇〇硬度」とは、水中の該当するもののイオンの量を表したものをさす
・マグネシウム硬度
水中のマグネシウムイオンの量を、これに対応する炭酸カルシウムの量に換算して試料1L中のmg数であらわす
・全硬度
水中のカルシウムイオン及びマグネシウムイオンの量を、これに対応する炭酸カルシウムの量に換算して、試料1L中のmg数であらわす
‣「カルシウム硬度」+「マグネシウム硬度」=「全硬度」という
ボイラーの蒸気圧力上昇時の取扱い
・点火後は、ボイラー本体に大きな温度差を生じさせないように、かつ、局部的な過熱を生じさせないように時間をかけ、徐々にたき上げる
・蒸気が発生し始め、白色の蒸気の放出を確認してから、空気抜き弁を閉じる
・圧力計の指針の動きを注視し、圧力の上昇度合いに応じて燃焼を加減する
・圧力計の指針の動きが円滑でなく機能に疑いがあるときは、圧力が加わっているときでも、圧力計の下部コックを閉め、予備の圧力計と取り替える
水位が安全低水面以下に異常低下する原因
・給水内管の穴が閉そくしている
‣ボイラ本体への給水ができなくなるため、ボイラ水位が安全低水面以下に異常低下する原因となる
・不純物により水面計が閉そくしている
‣水位が低下しても気づかないため、ボイラ水位が安全低水面以下に異常低下する原因となりえる
・吹出し装置の閉止が不完全である
‣閉止が不完全であると、水漏れする危険性があり水位が低下する恐れがある
・給水温度が過昇した
‣給水温度が急激に上昇すると、給水ポンプ内で蒸気となり給水不能となるので、安全低水面以下に異常低下する原因になります
ボイラー水の(間欠)吹出し
・炉筒煙管ボイラーの吹出しは、ボイラーを運転する前、運転を停止したとき、蒸気負荷が低いときに行う
‣内圧がない状態で吹出しを行っても、ボイラ水がうまく吹き出せない
‣最大負荷付近で吹出しを行うと、思いがけなく多量のボイラ水が排水されたり、急激な水位低下を引き起こす可能性があり危険
・温水ボイラーの吹出しは、他に温水を供給せず密閉した配管系統で使用する。そのため、水が蒸発する蒸気ボイラーとは異なり、ボイラー水を循環して使用するため、不純物は凝縮しない。そのため、スラッジの生成が少ないので吹き出しの必要が無い
・鋳鉄製蒸気ボイラーの吹出しは、運転中に吹出しを行ってはいけない
燃焼をしばらく停止してボイラー水の一部を入れ替えるときに行う
‣鋳鉄製蒸気ボイラーは保有水量が少ないので、運転中に吹き出しをするとボイラー壁が急冷されるので、破損に繋がります
・水冷壁の吹出しは、いかなる場合でも運転中に行ってはならない
‣水冷壁は内部にボイラ水があることによって、空だきを防いでいるが、運転中に水冷壁の吹出しを行うと、ボイラの空だきの原因となる。鋳鉄製ボイラと同様に、ボイラ休止中に行います
・給湯用温水ボイラーの吹出しは、運転中にスラッジ(かまどろ)等が沈殿することはないので、休止中に行う
・ボイラー運転中は、絶対に吹き出しをしてはいけません
・危険なので、1人で2基以上のボイラーの吹出しは禁止されています
‣吹出し作業を行っているときは、操作弁の近くで待機し、吹出し作業が終了したら早急に弁の閉止を行う必要がある
・直列に設けられている2個の吹出し弁を開けるときは、急開弁を先に開け、次に漸開弁を開ける
‣吹き出しを停止する場合は、逆操作を行って停止します
水中の不純物、障害
不純物や化合物
・溶存している酸素は、鋼材中の鉄と結びついてサビを生じさせるため、鋼材腐食の原因となります
・二酸化炭素は水に溶けると炭酸となり、酸性を示すため、酸に弱い鋼材を腐食させる原因になります
・スラッジ(かまどろ)とは、溶解性蒸発残留物が濃縮され、ドラム底部などに沈積した軟質沈殿物のことを指す
・懸濁物(水中に浮遊し、水に溶けない固体粒子)は、りん酸カルシウムなどの水に溶けにくい物質、エマルジョン化された鉱物油などが代表的
・スケールの熱伝導率は炭素鋼の熱伝導率より著しく小さいです。そのため、スケールが付着したままにしておくと、熱の伝達を妨げ、ボイラーの効率を低下させる
・スケール堆積により熱の伝達が妨げられることで本来、給水および蒸気に吸収されるべき熱が炉筒・水管に吸収されるようになり、そのため炉筒・水管が過剰に過熱され、最悪の場合破損に繋がる
水中の不純物によってスケールやスラッジが発生し、ボイラーにトラブルが発生することがある。水中の不純物(気体)では、溶存酸素や二酸化炭素があり、ボイラー内面を腐食させる。
蒸発して凝縮したボイラー水の中には、水のpHを下げる種々の化合物(カルシウムやマグネシウムの化合物、シリカ化合物、ナトリウム化合物、懸濁物など)がある。
これらの化合物や懸濁物は、スケール(伝熱面に固着した不純物)やスラッジ(固着せずボイラー底部に堆積する不純物)となって、ボイラーに障害を与える
酸洗浄
・酸洗浄の使用薬品には、塩酸などの酸性の薬品が用いられます
‣塩酸(HCl)が使用されます。水酸化ナトリウム(NaOH)はアルカリ性なので使用されません
・酸洗浄は、酸によるボイラーの腐食を防止するため抑制剤(インヒビタ)を添加して行う
・シリカ分の多い硬質スケールを酸洗浄するときは、洗浄助剤(シリカ溶解剤)を用いて、スケールを膨潤させる
‣膨潤とは、スケールを膨らませて柔らかくすること
・酸洗浄は、薬液に酸を用いて洗浄し、ボイラー内のスケールを溶解除去するもの
・酸洗浄作業中は、水素が発生するのでボイラー周辺を火気厳禁にします
‣水素は加熱により爆発する恐れがある
・酸洗浄を行った後は、薬液を洗い流すために水洗を行い、残留した酸を中和して錆を防ぐために中和防錆(せい)処理をします
‣酸洗浄→水洗→中和防錆処理の順
・シリカ分の多い硬質スケールを酸洗浄するときは、酸洗浄前に、所要の薬液で前処理を行い、スケールを膨潤させておく必要がある
‣前処理→水洗→酸洗浄→水洗→中和防錆処理の順
給水中に含まれる溶存気体(酸素・二酸化炭素など)が鉄と接触すると酸化して腐食を起こす。(水と酸素があれば鉄は腐食する)
そして、種類の異なる金属が水中で接触していると、電位差が発生し電流が流れることによりイオンが発生。一方の金属が腐食を起こす。
(腐食は電気化学的作用(酸化還元反応)により、鉄がイオン化することにより生じる)
・ボイラー水のpHを弱アルカリ性に調整することによって、腐食を抑制する
‣ボイラー水はかなりのアルカリ性である(ph 11.0~11.8)
ボイラー水の中に酸素が多いと、鉄が腐食して溶け出す。この溶け出しを減らすために、ボイラー水をアルカリ性にして腐食を防止する。
・腐食は、一般に電気化学的作用(酸化還元反応)などにより生じる
‣腐食とはつまり、鋼材の金属が腐食されることによって電子を放出してイオンになり、酸に含まれる水素が還元されて水素ガスを発生する酸化還元反応です
・腐食の形態には、全面腐食と局部腐食がある。
全面腐食は、金属表面全体が腐食する現象。局部腐食は、部分的に「点状」や「線状」に腐食する
・局部腐食にはピッチング(孔食)とグルービングなどがある。
ピッチングとは、金属表面に孔状に深い穴が開き、グルービングは、溝状に繋がって出来る局部腐食
・アルカリ腐食は、高温環境下で、水酸化ナトリウムの濃度が高くなると生じる
・ボイラー水のpHを酸消費量で調整してアルカリ性を維持することにより、水中での鉄のイオン化を減少させて腐食を抑制する
ボイラーの清掃
外面清掃
・すすの付着による水管などの腐食を防止する
内面清掃
・スケールやスラッジ(かまどろ)による過熱の原因を取り除き、腐食や損傷と、ボイラー効率の低下を防止する
・穴や管の閉塞による安全装置、自動制御装置などの機能障害を防止する
清缶剤
清缶剤は広い意味の言葉であるが、使用する目的は、ボイラー水中の硬度成分をスラッジ(かまどろ)に変え、スケールの付着を防ぐことである
‣ボイラー水に「溶解すること」ではない
補給水処理後の水は不純物が少なくなっているが、「pH」「溶存酸素」は調整されていない。したがって、そのままボイラーに使用すると、pHが低すぎてボイラー内面を腐食し、硬度成分によってスケールが付着しやすくなっている。そのため、清缶剤を給水及びボイラー水に投入して、腐食、スケールの付着などの障害を防止する。

①酸消費量付与剤
・低圧ボイラーでは酸消費量付与剤として、水酸化ナトリウムや炭酸ナトリウムが用いられる
‣ボイラ水が酸性に傾くと、鋼材が腐食するため、弱アルカリ性にさせます
‣塩化ナトリウムは中性であるため酸消費量を上げることはできない
②軟化剤
・軟化剤は、ボイラー水の中の硬度成分(カルシウム、マグネシウムイオン)を、不溶性の化合物(スラッジ)に変えて、これを微粒子状とし、スケールになって付着しないようにする薬剤です
沈殿したスラッジ(かまどろ)は、間欠吹出しなどで排出する必要があります
‣主にはカルシウム・マグネシウムなどの硬度成分を、炭酸塩やリン酸塩などの水に溶けにくい化合物に化学変化させるために使われます
・軟化剤には、炭酸ナトリウム、りん酸ナトリウムなどがある
‣リン酸ナトリウムを使用する理由は、ボイラー水中の硬度成分をスラッジ(かまどろ)に変えて、スケールの付着を防ぐ
‣炭酸ナトリウムは低圧力時に、リン酸ナトリウムは圧力に関係なく使用可能
‣リン酸ナトリウムは、ボイラ補給水中に含まれる硬度成分(カルシウム及びマグネシウム)を、水に溶けにくい物質である化合物に変える軟化剤として使用されています
・水素イオン指数( pH )を調整して、酸による腐食を抑制する
(有効成分:炭酸ナトリウム、リン酸ナトリウム)
・低圧ボイラーでは、ボイラ水中のシリカを可溶性の化合物に変える
(有効成分:炭酸ナトリウム、リン酸ナトリウム)
‣シリカはアルカリ性の化合物と反応して、水溶性の化合物に変わります
③スラッジ調整剤
・スラッジ調整剤は、ボイラー内で軟化により生じた泥状沈殿物(スラッジ)の結晶の成長を防止する
‣有効成分:亜硫酸ナトリウム、ヒドラジン、リグニン、デンプンなど
‣結晶化するとスケールとして付着するため、スラッジ調整剤を使用して物理的に除去する
④脱酸素剤
・脱酸素剤は、ボイラー水中の酸素を除去するための薬剤であり、腐食を防止します
・脱酸素剤には、タンニン、亜硫酸ナトリウム、ヒドラジンなどがある
‣これらは酸素によって酸化されやすい性質がありますので、その性質を利用している

補給水処理
ボイラー運転中は、水がどんどん蒸気となり出ていくので、水を補給していかなければなりません。ボイラーの給水タンクへ供給する補給水は、ボイラーで要求される水質基準に適合するようにあらかじめ処理を行っておく必要があり、単純軟化法が最も重要かつよく使用されている補給水処理法である
単純軟化法
・「強酸性陽イオン交換樹脂」を充填したNa塔に給水を通過させて、給水した硬水の硬度成分を樹脂のナトリウムと置換させる方法であり、軟化した水を軟化水という
・単純軟化法とは、軟化装置内に充填されている強酸性陽イオン交換樹脂により、水中の硬度成分(カルシウムやマグネシウム)を樹脂のナトリウムと置換させて、ボイラ補給水から硬度成分を除去する方法です
単純軟化法の軟化装置
・軟化装置は、補給水を「強酸性陽イオン交換樹脂」を充填したNa塔に補給水を通過させるものである
‣軟化装置は、通水することで強酸性イオン交換樹脂に含まれるナトリウムと、補給水中のカルシウム及びマグネシウムのイオン交換が行われるため、補給水中のカルシウム及びマグネシウムを除去することができる
・軟化装置は、強酸性陽イオン交換樹脂により、水中の硬度成分を樹脂のナトリウムと置換させる装置である
・軟化装置による処理水の残留硬度は、貫流点を超えると著しく増加してくる
貫流点とは、軟化能力がなくなる点をいう
・軟化装置による処理水の残留硬度が貫流点に達したら、通水を停止して再生操作を行います
‣イオン交換樹脂の再生操作は、通水しながら行うことはできません
・軟化装置の強酸性陽イオン交換樹脂の交換能力が低下した場合は、食塩水でイオン交換樹脂のイオン交換能力を回復させる。これを再生という
‣食塩水には「塩化ナトリウム」が含まれており、この硬度成分の除去に必要なナトリウムイオンを、すでに吸着したカルシウムイオン・マグネシウムイオンと置き換えることで、交換能力を回復させる。これを再生という
・軟化装置の強酸性陽イオン交換樹脂は、1年に1回程度、鉄分による汚染などを調査し、樹脂の洗浄及び補充を行う
‣イオン交換樹脂は、使用すると原水中に含まれる鉄分が付着(コーティング)するため、徐々に処理能力が落ちていきます。いったん付着した鉄分は、食塩水による再生では除去できないので、塩酸による酸洗浄を行って、イオン交換樹脂の能力を回復させる必要がある。また、酸洗浄でも能力を回復させられない場合には、樹脂を補充するなどして、軟化装置の能力を維持する
装置、点検、その他
水面測定装置の取扱い
- 水面計の機能試験は、毎日行う
- プライミングやホーミングが生じたときは、水面計の機能試験を行う
- 運転開始時の水面計の機能試験では、点火前に残圧がある場合は、点火直前に行う
- 運転開始時の水面計の機能試験は、点火前に残圧がない場合は、たき始めて蒸気圧力が上がり始めたときに行う
‣他には蒸気圧力が上がり始めた時のほか、プライミング発生時、ガラス管の取り替え時などに行う - 水面計のコックを開くときは、ハンドルを管軸に対し直角方向にする
- 水面計のコックは、運転時にハンドルが全て下方になるように、ハンドルが管軸と直角方向の場合に開とする
‣一般のコックとは異なっている
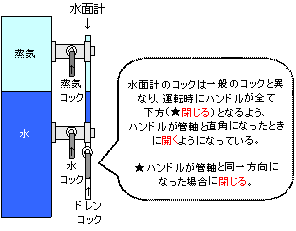
- 水柱管の連絡管の途中にある止め弁は、誤操作を防ぐため、全開にしてハンドルを取り外しておく
‣止め弁では、開閉を間違えないために、普段は全開にしてハンドルを取り外しておきます。弁を開閉する時にのみ、ハンドルを取り付けます - 水柱管の水側連絡管の取付けは、ボイラー本体から水柱管に向かって上がり勾配となるよう配置する
- 水側連絡管のスラッジ(かまどろ)を排出するため、水柱管下部の吹出し管により、毎日1回吹出しを行う
- 水側連絡管で、煙道内などの燃焼ガスに触れる部分がある場合は、その部分を耐熱性のある材料で防護する
‣不燃性の材料では無く耐熱性。不燃性の材料は、必ずしも耐熱性があるとは限らない

水面計の機能試験実施条件
・2個の水面計の水位に差異が認められたとき
・水面計の水位の動きがにぶく、正しい水位を示しているかどうか疑いがあるとき
・ガラス管の取り替え、そのほかの補修を行ったとき
・ボイラーの取り扱い担当者が交替したとき
・キャリオーバが生じたとき
‣キャリオーバとは、本来蒸気しかない主蒸気配管に水分が入ってしまう現象をいう
‣原因は、プライミング(水気立ち)、 ホーミング(泡立ち)、シリカの選択的キャリオーバに大別
‣キャリオーバは、ドラムから後工程に影響があります
安全弁の調整および試験
ばね安全弁の調整
・安全弁の調整ボルトを定められた位置に設定した後、ボイラーの圧力をゆっくり上昇させて安全弁を作動させ、吹出し圧力及び吹止まり圧力を確認します
・安全弁が設定圧力になっても作動しない場合は、直ちにボイラーの圧力を設定圧力の80%程度まで下げ、調整ボルトを緩めて再度試験します
‣安全弁の吹き出し設定ナットは、締め込むと設定圧力が上昇し、緩めると設定圧力が下降する
・最高使用圧力の異なるボイラーが連絡している場合、各ボイラーの安全弁は、最高使用圧力の最も低いボイラーを基準に調整します
・安全弁の手動試験は、最高使用圧力の75%以上の圧力で行う
安全弁が2個ある場合の調整
・ボイラー本体に安全弁が2個ある場合は、1個を最高使用圧力以下で先に作動するように調整し、他を最高使用圧力の3%増以下で作動するように調整します
‣二つ安全弁を使用する場合、ある程度の幅をつける必要があります
過熱器用安全弁の調整
・ボイラー本体の安全弁より先に吹出すように調整する
‣本体安全弁が先に吹くと、過熱器を焼損させる恐れがあるため。過熱器の安全弁を出口側管寄せに取り付けるのもそのためである
エコノマイザの逃がし弁(安全弁)の調整
・ボイラー本体の安全弁より高い圧力に調整します。
‣エコノマイザの逃し弁が先に作動すると、エコノマイザの逃し弁から水が吹き出されてしまい、ボイラー本体の給水が足りなくなるためです
ボイラーのばね安全弁に蒸気漏れが生じる原因
・弁体と弁座の間に、ごみなどの異物が付着している
・弁体と弁座のすり合わせが悪くなっている
・弁体と弁座の中心がずれて、当たり面の接触圧力が不均ーになっている
・ばねが腐食して、弁体を押し下げる力が弱くなっている
‣ばねを締めすぎていると作動がうまくいかないことがありますが、蒸気漏れの原因とはならない
ボイラーの水位検出器の点検及び整備
・電極式では、1日に1回以上、水の純度の上昇による電気伝導率の低下を防ぐため、検出筒内のブローを行う
・電極式では、1日に1回以上、ボイラー水の水位を上下させ、水位検出器の作動を確認する
・電極式では、1年に2回程度、検出筒を分解し内部掃除を行うとともに、電極棒を目の細かいサンドペーパーで磨く
‣電極棒の腐食を除き、伝導率を上げます
・フロート式では、1日に1回以上、フロート室のブローを行う
・フロート式のマイクロスイッチ端子間の電気抵抗をテスターでチェックする場合、抵抗がスイッチが閉のときはゼロで、開のときは無限大であることを確認する
‣電気関連の技術用語になりますが、スイッチオフが「開」、スイッチオンが「閉」と呼称します。ちなみに、デジタルテスターでの無限大は、OL(オーバーレンジ)で表される
ボイラー水位が安全低水面以下に異常低下する原因
・不純物により水面計が閉塞していると、正しい水位を検出できないため、ボイラ水位が安全低水面以下に異常低下する原因になりえます
・吹出し装置の閉止が不完全であると、吹出し管からボイラ水が不必要に排出されるため、ボイラ水位が安全低水面以下に異常低下する原因になりえます
・蒸気を大量に消費すると、給水と蒸気発生のバランスが崩れて、給水が追い付かなくなれば、ボイラ水位が安全低水面以下に異常低下する原因になりえます
・給水内管の穴が閉塞していると、ボイラへの給水ができなくなるため、ボイラ水位が安全低水面以下に異常低下する原因になりえます
‣気水分離器が閉塞していても、水位の異常低下にはつながりません
ボイラーのたき始めに燃焼量を急激に増加させてはならない理由
ボイラー本体の不同膨張を起こさないため
‣ボイラ本体が冷えているたき始めのときに、急激に部分的に熱が加わって、鋼材がいびつに膨張して歪む現象であり、たき始めはゆっくりと熱を加える
①高温腐食
重質燃料を使用した時、腐食性配分が高温の管外面に付着することにより起こる腐食のこと
②ホーミング
ボイラ水中に含まれる不純物が原因で、ボイラ水が泡立つ現象
③スートファイヤ
スート(すす)が着火する現象で、これを防ぐために定期的にスートブロー(すす吹き)を行う
④ウォータハンマ
急激な水圧変動によって配管の曲部などに流れが当たって、ハンマーで打ったような音を出す現象
スートブローの注意点
・スートブローの回数は、燃料の種類、負荷の程度、蒸気温度などに応じて決める
・スートブローを行ったときは、煙道ガスの温度や通風損失を測定して、その効果を確かめる
・スートブローの蒸気は乾いたものを用いる。水分を含んでいるとスートブローを行った部分にすすが付きやすくなります
・スートブローは、一箇所に長く吹き付けないようにして行います。一箇所に長く吹き付けると、吹き付けた箇所の損傷につながる恐れがあります
・スートブローは、最大負荷よりやや低いところで行う。ある程度の圧力がないと、蒸気が出づらいです
ボイラーのガラス水面計の機能試験を行う時期
・点火前に残圧がない場合は、たき始めて蒸気圧力が上がり始めたときは機能試験を行う必要がある
・ガラス管の取替えなどの補修を行ったとき
・水位の動きが鈍く、正しい水位かどうか疑いがあるときは機能試験を行う
・キャリオーバ(プライミングやホーミング)が生じたときは水位計に泡が入り込んできている可能性があるため、機能試験を行う必要がある
‣二組の水面計に差異がなく、動作にも問題がない場合は、そのガラス水面計は正常に動作している
油だきボイラーが運転中に突然消火する原因
炉内温度が高すぎる場合は、燃焼においては十分にされているので、突然の失火の原因にはならない
・燃焼用の空気量が多すぎる
・噴霧式バーナの場合、燃焼用空気の噴射空気圧が高すぎると不安定燃焼となり、失火の原因となる
‣噴霧空気の圧力が強すぎると、火炎を空気で吹き消してしまう可能性がある
・油ろ過器が詰まっている
‣油ろ過器が詰まっていると、燃料の供給ができなくなる
・燃料弁を絞りすぎている
・燃料油の温度が低い
‣燃料油の温度が低すぎると、燃料が十分霧化できなくなるため
・燃料油に水分が多く含まれている
‣水分は燃焼しないので、突然消火の原因となる
‣炉内温度が高すぎるのは、消火に関係ありません
キャリオーバが発生する原因
・ボイラ水位が高水位であると、水位が蒸気取り出し口に近いため、水滴と蒸気が混入してキャリオーバに至る
・蒸気負荷が過大であると、ボイラ水が沸騰した状態となり、水位変動が起こりプライミングを起こしてキャリオーバに至る
・主蒸気弁を急開すると、水位変動が起こり、高水位になる
・ボイラ水に油脂分が多く含まれていると、フォーミングが起こりやすくなり、キャリオーバに至る
・ボイラー水の純度が低いと、不純物が多い
・ボイラ水が過度に濃縮されていると、不純物濃度が増えてフォーミングが起こりやすくなり、キャリオーバに至る
キャリーオーバの害
・蒸気とともにボイラ水が蒸気配管に入るため、蒸気の純度を低下させます
・プライミング(気液同伴)やフォーミング(泡立ち)によってボイラ水全体が著しく揺動するため、水面計の水位が確認しにくくなります
・水位制御装置がボイラー水位が上がったものと認識し、ボイラー水位を下げるため、低水位となる
・自動制御関係の検出端の開口部若しくは連絡配管の閉塞又は機能の障害を起こします。また、安全弁、圧力計、水面計にも機能異常が見られます
‣不純物が付着しやすくなるため
・ボイラー水が過熱器に入り、蒸気温度が低下したり、過熱器の汚損や破損を起こします
燃料油用遮断弁(直動式電磁弁)の作動原理
燃料油用遮断弁は、電磁石の力で弁体が開閉する電磁弁が用いられる。コイルに通電することで電磁力が発生し、弁体(可動コア)が上がり「開」状態となります。
電磁弁の故障が発生した時には、コイル(電磁石)の磁力が無くなり、弁体はばねの押し付け力によって閉まるので、燃料油を止めます
燃料用遮断弁は、正常時の燃焼中に通電状態で「開」となり、停止時または、異常時(電源喪失)に遮断弁が「閉」となる、フェールセーフの動作を実現している
燃料油用遮断弁(直動式電磁弁)の遮断機構の故障の原因
・電磁コイルの絶縁性能が低下している
‣電磁弁が正常に機能しなくなるため、遮断機構の故障の原因となる
・弁棒が曲がっている
‣弁の動作に支障をきたすため
・燃料中の異物が弁へ かみ込んでいる
‣弁が完全に閉止することができないため
・弁座が変形したり損傷したりしている
‣弁座が変形すると機能低下につながり、故障の原因になる
‣(注)バイメタル・ダイヤフラムは、燃料油用遮断弁に使用していません
ボイラーに給水するディフューザポンプの取扱い
・ポンプの吐出し側の圧力計により、給水圧力を確認する
・運転前に、ポンプ内及びポンプ前後の配管内の空気を十分に抜き(エア抜き)、ポンプ内部を補給水で満たす
・起動は、吐出し弁を全閉、吸込み弁を全開にした状態で行い、ポンプの回転と水圧が正常になったら吐出し弁を徐々に開き、全開にする
‣ウォータハンマを防ぐため
・運転中は、ポンプの吐出し圧力、流量及び負荷電流が適正であることを確認する
・メカニカルシール式の軸については、水漏れがないことを確認する
・グランドパッキンシール式の軸については、運転中、滴る程度に水漏れがあることを確認する
‣水を少しだけ漏らす理由は、この水がポンプ軸の冷却水となるため
・運転を停止するときは、吐出し弁を徐々に閉め、全閉にしてから、ポンプ駆動用電動機を止める
‣【停止時】吐出し弁を徐々に閉止 ⇒ ポンプ停止 ⇒ 吸込み弁を閉止
‣起動時と逆の手順が正しい停止方法
水圧試験
水圧試験には、ボイラーの工作時に行う構造上の耐圧試験と、設置時に、漏れなどを確認する試験圧力がある
・ボイラーを製造した場合の水圧試験は、通常、最高使用圧力の1.5倍の圧力で行う
・すでに設置されているボイラーの水圧試験は、最高使用圧力又は常用圧力の1~1.1倍程度の圧力で行う
ボイラー休止中の保存法
満水保存法
・満水保存法は、休止期間が3か月程度以内の短期間休止する場合に採用される
・満水保存法は、凍結のおそれがある場合には採用できない
‣凍結によってボイラ水が膨張し、ボイラ本体を破損させるため
・保存剤を所定の濃度になるようにボイラーに連続注入するか又は間欠的に注入する
・保存水(ボイラー水)の管理を行うために、月に1〜2回、pH、鉄分及び薬剤の濃度を測定する
乾燥保存法
・乾燥保存法は、3か月以上の長期間休止する場合に採用される
・シリカゲル、活性アルミナなどの吸湿剤を容器に入れて、ボイラー無いの数か所に配置、密閉する
・ボイラー水を全部排出して内外面を清掃した後、少量の燃料を燃焼させ完全に乾燥させる
・ボイラー水を全部排出して内外面を清掃した後、ボイラー内に蒸気や水が漏れ込まないように、蒸気管、給水管などは確実に外部との連絡を遮断する



コメント